スマートプラグでできることは?基本的な使い方と利用時の注意点

スマートプラグとは、スマートフォンやスマートスピーカーなどで家電の電源を遠隔操作できるスマートデバイスです。通常、スマートデバイスをインターネットにつなぎ遠隔操作するためには、専用のアプリケーションが必要で、特定のベンダー製品やサービスに依存していました。メーカーごとに製品やサービスを買い揃える必要がありましたが、最近のスマートデバイスには、ベンダーフリーなスマート家電も出てきました。
この記事では、スマートプラグについての基本的な特徴や使い方、使用する際の注意点を中心に紹介するほか、最近のスマート家電の動向についてもお伝えします。
スマートプラグとは?基本機能と使い方
スマートプラグの基本機能
スマートプラグとは、家電の電源管理をスマートフォンやパソコンから遠隔操作できる電源プラグです。電源に設置したスマートプラグをアプリで設定し、操作したい家電を接続することで準備は完了です。無線ネットワークを介してスマートフォンやタブレットからスマートプラグの電源のON/OFFをアプリケーションからコントロールできるようになります。これにより接続している家電の電源も連動させることが可能になることから、家電の電源管理ができるようになります。スマートプラグ製品によっては電力の使用状況をリアルタイムで把握できるものもあります。
主に、下記のような家電がスマートプラグに対応しています。
・加湿器、除湿機
・扇風機、サーキュレーター
・充電器
・照明機器 等
スマートプラグ導入時のポイント
アプリの使いやすさ
スマートプラグの多くは専用アプリを使用して管理します。そのため、アプリの操作性や日本語対応の有無を確認し、使いやすいものを選ぶことが大切です。
セキュリティ
スマートプラグをインターネット経由で操作するため、セキュリティ対策も重要です。暗号化通信や不正アクセスを防ぐ機能が備わっている機器を使用しましょう。
Matter対応製品
Matterとは、異なるメーカのスマートデバイスが互いにシームレスに通信できるようにするための規格です。Apple、Google、Amazon、Samsungなど、別々のアプリケーションで操作していたスマートデバイスを、Matter対応であれば、どのアプリケーションからでも操作できるようになります。メーカを気にせず使用できるようになるほか、標準でデータ暗号化などのセキュリティ対策が取られており、ユーザが安心して利用できるように設計されています。
使いやすさやセキュリティが考慮されているMatter、サポート対象機器も順次追加されていることから、今後の家庭への普及が期待されています。
スマートプラグ使用時の注意点
対応機器の確認
家電のタイプによってはスマートプラグを使用できない場合があります。
スマートプラグの最大出力を超える可能性がある製品、火災や感電の恐れがある電熱器は電気用品安全法(PSEマーク)により禁じられているため絶対に使用しないでください。
【使ってはいけない家電】
・こたつ
・電気ストーブ
・電子レンジ
・電気ケトル
・ドライヤー 等
電気用品安全法(PSEマーク)
電気用品安全法とは、電気用品による火災や感電などの事故を防止することを目的とした法律です。
電気用品の製造、輸入、販売を規制するとともに、民間事業者の自主的な安全確保を促進する仕組みとなっており、販売事業者は、電気用品安全法に定める表示が付されていることを確認する義務があります。
この電気用品安全法の基準をクリアした電気用品に表示されているのが「PSEマーク」です。「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の2つの区分があり、経済産業省のサイトで対象用品の一覧が公開されています。
【特定電気用品】
特定電気用品とは、その構造又は使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれの高いものとして、
①長時間無監視で使用されるもの、②社会的弱者が使用するもの、③直接人体に触れて使用するもの
が指定されています。
例) ゴム絶縁電線、温度ヒューズ、コンセント、電気温水器、電気ポンプ、高周波脱毛器、電動式おもちゃなど
特定電気用品一覧 (経産省):
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/specified_electrical.html
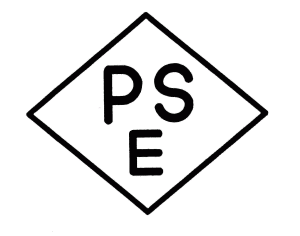
【特定電気用品以外の電気用品】
電気用品安全法の対象になっている電気製品のうち、特定電気用品を差し引いた電気用品を指します。
例) こたつ、電気ストーブ、電気レンジ、電動ミシン、サーキュレータ、扇風機、除湿機など
特定電気用品以外の電気用品一覧 (経産省):
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/non_specified_electrical.html
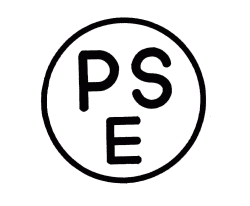
電気用品安全法では、電熱器を含む特定の電気用品をスマートプラグにつなぎ、音声などでリモート操作することが禁じられています。また、電気用品安全法に抵触していない製品であっても、スマートプラグの電源ON/OFFだけでは家電の起動まで出来ないテレビなどの家電がある他、エアコンなど、スマートプラグの定格電力を上回るケースもあります。スマートプラグならびに接続デバイスのご使用にあたっては、必ず双方のデバイスのスペックを確認してからご利用ください。
※スマートプラグを用いたリモート操作が禁止されている場合でも、モニタリング機能などは利用可能です。
スマートプラグの活用例
消費電力監視による存否確認
スマートプラグの製品によっては、消費電力をリアルタイムで確認できる機能があります。この機能を使えば、家電の使用状況を把握できるため、一人暮らしの高齢者が毎日決まった時間にテレビ等を使用している場合、その消費電力をモニタリングすることで、存否確認が可能になります。
また長時間電気が使われていない場合、異常を検知してスマートフォンなどで通知を受け取ることができます。音声アシスタントと組み合わせれば、手が届かない場所にある電化製品の操作もサポートできます。
▲D-Link製スマートプラグの消費電力画面例
まとめ
スマートプラグは、無線機能を備えた電源プラグで、コンセントに挿すだけで遠隔から家電の電源管理を行えるデバイスです。
異なるメーカ同士のスマートデバイスが通信できるようにするための共通規格「Matter」の導入も進められており、今後の更なる普及が期待されています。
ただしスマートプラグは、電熱器など一部の家電には使用できないため、利用時には注意が必要です。
スマートプラグを上手に活用することで、日常生活の利便性向上が期待できます。導入を検討する際は、機能や安全性をしっかり確認し、最適なものを選びましょう。

